吉川広家の居城であった。関ケ原以後、広家は、なんとか毛利家の所領として
長州37萬石を保持したが、かえって毛利家に恨まれることになった。1国1城と
して藩の城は萩に移ったので、岩国城は廃城となった。
支藩として岩国藩が置かれた。



天慶の乱の際に藤原純友の家臣の築城という説がある。
文献上では大内氏家臣内藤氏の築城。その後、毛利長府藩の支城となったが、
一国一城で廃城となった。
現在は公園化されていて整備されている。数年前に撤去した水族館の名残もある。
石塁は部分的に綺麗に残る。
尚、天守台跡に登る木製の階段が朽ちかけたせいで立ち入り禁止となっているが、
2mの石垣を登ることは可能であった。

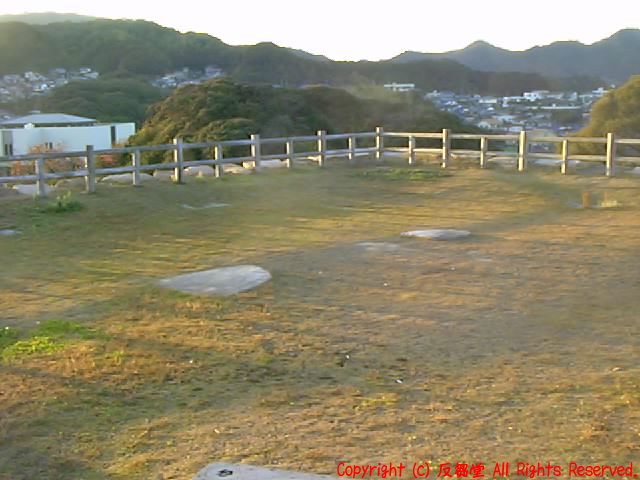


室町中期に深川城主鷲頭弘忠が築城したと推測されている。
文安5年(1448)に大内教弘が深川城を攻める以前に落城したと推測されるが定かでない。
現在、長門市役所裏にある比高22mの小山で墓地から登って行ける。
いきなり堀切があり(左端画像)、急な坂を登ると(帰路急斜面故に滑った)、
2段からなる曲輪があり(画像中央)、そこが本丸のようである。
竹林や薮などではっきりしない所も多い。



関ケ原の戦いに戦わずして敗れた、毛利輝元が慶長9〜13年(1604〜08)に築城した。
文久3年(1863)に敬親が山口に移るまで本城であった。
麓に天守閣、本丸、二の丸、三の丸があり、南以外海に囲まれている。
標高143mの指月山には詰丸があり、
タガネを打ち込んだ跡のある巨岩も残る(右端画像)。
また天水貯蔵の水溜まりも残る。
詰丸には搦め手もあるが、ここから山中櫓に行けると思い、下ると、
次第に道は定かでなくなり、さらに薮が酷くなり、なんとか志都岐山神社裏に出た。
お薦めできない。





築城の時期は詳細には分っていない。
現地案内板によれば、文明2年(1470)陶弘護が三本松の吉見氏に備え築城したとある。
天文19年(1550)陶晴賢は大内義隆に叛旗を翻し、翌年義隆を討った。
が、弘治元年(1555)毛利氏を攻めるために安芸に攻める際に、
嫡子五郎長房を当城に守らしめた。
10月1日厳島で晴賢が討たれると、翌弘治2年(1556)2月20日杉重輔に攻められ、
長房は城を捨て、龍文寺に逃れたが、自刃した。
弘治3年(1557)毛利氏は長屋小次郎を城番として守らせたが、
山口の毛利与三・野上内蔵助に攻められ落城した。
その後、再び毛利氏が落城させ、廃城となった。
東西に伸びる尾根上に残る。麓から車道で行け、地元の方々の宝になっているようで、
道々にはいろいろな俳句や短歌など途切れることなく迷う心配はない。
道路の末端は二の丸で駐車場となっている三の丸は遺構は消滅しているようである。
一方、ここから本丸にかけて10段以上の曲輪が続き(左端画像)、
その北面の斜面には今はだいぶ浅くはなっているが、
10条以上の畝状竪堀が残る(中央画像)。
最高部の本丸からさらに奥である西へ行くと石塁の残る西の丸(右端画像)、
薮化している蔵屋敷跡が残る。
当時は南側はすぐ海であったようである。



このページの著作権は、作者に帰属します。 画像などの2次利用は御遠慮下さい。